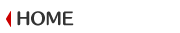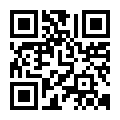活動日誌−活動日誌
【14.03.01】 今日はビギニデー、新聞各紙(3社)が社説で意見を(赤旗は2月21日に掲載)
桑名からも何人かが、焼津市でのデモ行進と墓前祭に参加
焼津は、私の第2の故郷です。
大学を出てから、山之内製薬に入り、最初の赴任先が焼津にある最新の工場でした。
1年と3ヶ月ほどいました。
赤旗新聞を読みだしたのはその頃からです。
焼津がマグロの町だとは知っていましたが、ビギニについての意識はそんなにありませんでした。
数年前には、桑名から3人で参加しました。
昨年も、焼津に寄り、旧友と杯を交わしました。
焼津の駅前はマンション群でコンクリートジャングルです。
桑名をこうしてはならないと決意もしました。
ビキニ被曝―60年後も続く非人道性 朝日新聞社説
太平洋のビキニ環礁で米国が水爆実験をしてから、きょうで60年たつ。
マグロ漁船・第五福竜丸の被曝も人々の記憶から遠ざかるが、事件は決して過去の出来事ではない。軍事用であれ民生用であれ、核エネルギーが牙をむいた時の恐ろしさを見つめ直す機会にしたい。
広島に投下された原爆の1千倍の威力を持つ水爆は、甚大な量の死の灰をまき散らした。米ソを中心に核軍拡がこうじると、人類は滅亡しかねない。危機感が世界に広がった。
日本では「放射能マグロ」や、死の灰を含む雨が国民に衝撃を与えた。原水爆禁止運動が起こり、広島、長崎の原爆被害への関心も改めて高まった。
ただ事件は、大気圏内で80年までに500回以上繰り返された核実験の一つに過ぎない。
最近明らかになった米公文書によると、米国は水爆実験に伴い、死の灰の観測点を世界122カ所に設けていた。地球の汚れがどの程度かを調べるのが大きな目的だった。いったい、人間への被害を抑える努力がどこまで尽くされたのか。
実験場となったビキニ周辺では島民が故郷を追われた。60年以上たっても帰れない。世界各地の旧実験場周辺でも健康被害を訴える住民らが多くいるが、核保有国は概して冷淡だ。
核は国の安全上必要である。その大義名分のもと、人々は被害の受忍を迫られる。核が本質において非人道的であることを思わずにいられない。
ビキニ事件の10カ月後、米国が日本に7億円超を払うことが決まった。賠償責任は認めず、「見舞金」の形をとった。
現場近海には第五福竜丸以外にのべ1千隻ほどの日本の船舶がいたといわれる。ただ、補償されたのは漁業被害の一部だけだった。被曝の健康影響を疑う元船員や研究者らが実態解明を求めているが、日本政府も「終わったこと」という態度だ。
ただ近年公開された公文書で、世論の反米化を恐れた米国が、日本の汚染マグロ調査をやめさせるよう働きかけるなど、早い幕引きをめざした外交の内幕が明らかになってきている。
核エネルギーが暴走すれば、人や社会には計り知れない被害が生じる。その実態をなるべく隠そうとするのは、兵器でも、原発でも、核を握る側の性にも思える。
ビキニで起きたことに目をこらそう。核と人間の関係を考えていくには、事実を検証し、被害を一つひとつ明らかにしていくことが不可欠である。
ビキニ被ばく60年 核廃絶への決意新たに 毎日新聞社説
米国が太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で行った核実験で、付近で操業していた日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員23人が被ばくした事件から1日で60年になる。日本にとっては広島、長崎への原爆投下に続く核被害となり、原水爆禁止運動が高まる契機になった。事件を風化させず、核廃絶への取り組みを進める決意を新たにしたい。
1954年3月1日、第五福竜丸の乗組員は、水爆実験による大量の放射性物質「死の灰」を浴び、無線長の久保山愛吉さんが半年後に死亡した。米政府が「見舞金」として日本側に200万ドルを支払うことで政治決着したが、乗組員への十分な補償や調査は行われていない。米国はこの海域で46〜58年に計67回の核実験を行い、延べ1000隻の日本漁船が被災したと言われるが、実態は今も解明されていない。
54年の核実験では、風下にあったロンゲラップ環礁の島民も被ばくした。強制移住後、いったん帰還したが健康被害が続出し、再び避難したままになっている。マーシャル諸島の首都マジュロでは1日、こうした被ばく者の追悼式典が開かれ、第五福竜丸の元乗組員らも参加する。原発事故があった福島県からの参加者も予定されているという。
ストックホルム国際平和研究所によると、減少傾向にあるとはいえ今なお世界には1万7000発を超える核兵器がある。オバマ米大統領は5年前に「核なき世界」を目指すと演説したが、その実現への道のりはなお遠い。
現在、核兵器に関する国際条約は保有国を米国、英国、フランス、ロシア、中国の5カ国に限定した核拡散防止条約(NPT)だけだ。5カ国の核保有独占に反発するインド、パキスタンやイスラエルは加盟しておらず、北朝鮮は2003年に脱退宣言した。地下核実験も含む核実験全面禁止条約(CTBT)は96年に国連総会で採択されたが、米国、中国などが批准せず条約は発効していない。インド、パキスタン、北朝鮮はこの条約の採択後も核実験を行い、調印さえも拒否している。
だが、非核保有国による核廃絶への粘り強い取り組みは続いている。2月にはメキシコで、日本など146カ国が参加して核兵器の人道的影響に関する国際会議が開かれた。4月には広島で、段階的な核軍縮を目指す「軍縮・不拡散イニシアチブ」の第8回外相会合が開かれる。
日本は一方で米国の「核の傘」に依存するというジレンマを抱えているが、核廃絶を目指す国際的な取り組みと積極的に連携し、少しでも「核なき世界」へ前進できるよう、核保有国への訴えを重ねたい。
ビキニ60年 「死の灰」は今も、の怖さ 中日新聞社説
米国が太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験で日本の漁船が「死の灰」を浴びた惨禍から六十年。被ばくした元乗組員や周辺の島民らの苦悩は今も続く。核は許されない、その思いを新たにしたい。
東京・井の頭線渋谷駅の連絡通路に巨大壁画がある。岡本太郎さんの「明日の神話」。水爆さく裂の瞬間がマグロ漁船「第五福竜丸」とともに描かれた代表作だ。
「福竜丸」は一九五四年三月一日、中部太平洋のマーシャル諸島で行われた米国の水爆実験で、放射能を含む「死の灰」を浴びた。威力は広島に投下された原爆の約千倍。二十三人の乗組員は全員急性放射線障害を発症し、四十歳だった無線長の久保山愛吉さんが半年後、入院先の東大病院で亡くなった。生き残った多くの人もその後肝臓がんなどで亡くなり、生存する七人も病魔と闘っている。
水爆実験で被災した日本漁船は福竜丸だけではない。米ソ冷戦下、四八年から五八年まで行われた実験は六十七回に及び、日本政府の調査では少なくとも八百五十六隻の被ばくが判明している。福竜丸の被ばく後も実験を知らない漁船が海域で操業していた。
しかし、福竜丸が強調される一方で、他の被災漁船の乗組員の被ばくは軽視され、事件は矮小化された。五五年に米政府が日本政府に支払った慰謝料は、汚染魚の買いとりや廃船費などに充てられたが、乗組員の健康について追跡調査などは行われなかった。
ビキニ事件は広島、長崎の原爆投下に続く核被害として、核廃絶運動の原点となりながら実態は明らかにされず、九五年に施行された被爆者援護法の対象にもならなかった。一部の被災漁船の乗組員の調査ではがんによる死亡が多発し、内部被ばくによる晩発性の障害に苦しんでいた。
何の補償も、救済もない。差別や偏見を恐れ、被ばくの事実を語れずに生きてきた。仲間を失い、高齢になって健康調査に協力を申し出た人も出ている。時間との闘いだ。ビキニの被害は今も続く。忘却してはならない。
死の灰で苦しむのは実験地にされた太平洋の島民も同じだ。米国の進める帰還政策に従う間に甲状腺異常や白血病などが広がった。福島原発事故の被害も過小評価し、同じ轍を踏んではならない。
大切なふるさとを奪い、健康や生活を壊す。生きる権利を蝕む核−。この問題とどう向き合うのか。静かに考えてみたい。
3・1ビキニデー被爆国の責任が問われている しんぶん赤旗主張2月21日(金)
3月1日は南太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で1954年にアメリカがおこなった水爆実験で、日本のマグロ漁船などが被災して60年にあたります。3・1ビキニデーは、広島と長崎に原爆が投下された8月6日と9日のヒロシマ、ナガサキの日とともに、核兵器廃絶への決意をあらたにする日です。
この核実験で被ばくしたマグロ漁船・第五福竜丸の無線長、久保山愛吉さん(当時40歳)が、「原水爆による犠牲者は、私で最後にしてほしい」とのべて亡くなったことは内外に大きな衝撃をあたえました。太平洋で水揚げされたマグロが放射能で汚染されていたことも重なり、核兵器と核実験にたいする国民の憤りと不安は一気にひろがりました。やがてそれは当時の有権者の半数にもあたる3200万人もの署名や第1回原水爆禁止世界大会(55年)の開催へと発展していったのです。
ビキニ被災は、第五福竜丸だけでなく、近海で操業していたのべ1000隻もの漁船の乗組員に及びました。核実験場とされてきた現地の島民は、現在も汚染された故郷に戻れていません。ロンゲラップ環礁では、2万人以上が被ばくしたといわれ、多くの人々がいまだに後遺症に苦しめられています。ヒロシマ、ナガサキの原爆被害とともに、核兵器がいかに人類と共存できないかをしめしたのがビキニ水爆実験被災です。
いま国際政治の舞台でも、核兵器の残虐性とその甚大な被害に目を向け、使用の禁止と廃絶を訴える声が広がりつつあります。2月13、14日メキシコで、核兵器の使用がもたらす「人道上」の影響についての国際会議が開かれました。146カ国の政府代表が参加し、核兵器が人間や環境などにもたらす深刻な影響を議論しその禁止と廃絶をよびかけました。日本から被爆者の代表も参加して訴えました。125カ国の連名で「核兵器の人道上の影響に関する共同声明」も昨年発表されています。「核兵器全面禁止のアピール」署名など核兵器禁止条約の交渉開始を求める世論も広がっています。
ヒロシマ、ナガサキに続き、三たび原水爆の被害を体験した日本には、核兵器の非人道性とその全面禁止・廃絶を訴える特別の責務があります。ところが日本政府は、ビキニ被災の実態解明にも背を向け、一部の被災者へのわずかな見舞金で幕引きをはかりました。それは、反核世論をおさえ、日本を核戦争の足場にするアメリカの意向にそったものでした。ビキニ被災の直後50年代の原発導入のねらいの一つも、そこにありました。
安倍政権はアメリカの「核の傘」が必要だといいます。さらには「個別的・集団的自衛権に基づく極限的な状況」なら、核兵器を使用してもよいといいだしています。「いかなる状況」でも核兵器を使用すべきでないというのが被爆国としての立場ではないでしょうか。アメリカの核戦略につきしたがい、核兵器廃絶の流れに背をむける日本政府の態度が、いまきびしく問われています。
広島・長崎の被爆から70年に開かれる来年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向け、被爆国の運動を発展させるうえでも、ビキニデー集会の成功が重要です。