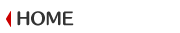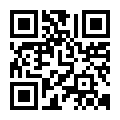活動日誌−活動日誌
【14.02.13】 昨日報道された、診療報酬の2014年度改定案
入院から在宅へ患者追い出しを進める。
昨日報道された、診療報酬の2014年度改定案は、桑名市が進めている在宅医療は地域包括ケアシステム出発点となるもの。
入院から在宅へ患者の追い出しを進める、挙句の果ては看取りを自宅でさせようとする。
大変な問題が発生しようとしている。
2025年問題と言う、超高齢化の中で。
新聞各紙が報道、社説で見解発表
病床削減 患者追い出し 中医協 診療報酬改定を答申 しんぶん赤旗
中央社会保険医療協議会は12日、公的医療保険から医療機関に支払われる診療報酬の2014年度改定案を田村厚労相に答申しました。「入院から在宅へ」という厚労省の方針に沿って病床の大幅削減や大病院の外来縮小など医療費の徹底削減を狙う内容です。
看護配置の手厚い「7対1病棟」(患者7人に看護師1人)や「10対1病棟」については要件を厳しくし、入院が90日を超えると報酬が下がるようにして患者追い出しをすすめます。「7対1病棟」には退院患者の割合などを基準に加えて締め付け、2年間で36万床のうち9万床を減らす方針です。療養・精神病棟についても在宅復帰などを評価に加えて削減をはかります。
大病院の外来診療について、紹介状を持たない受診が多ければ報酬を減らすなど縮小をはかります。
「主治医」の役割を果たす診療所や中小病院向けの「地域包括診療料」を導入。主治医となる医療機関を一つに限定するため、受診する権利が侵害されるなど医療現場を混乱させ、地域医療を衰退させかねない危険性が指摘されています。
うがい薬だけの処方を保険対象外とし、国民皆保険制度の空洞化につながる内容が盛り込まれています。
一方、要介護者の「維持期リハビリ」の介護保険への移行については、「リハビリは医療行為」との批判に押されて医療保険で継続。前回導入された有床診療所の管理栄養士の配置義務付けは撤廃し、加算措置に変えます。また、消費税への対応では医科で初診料を120円、再診料を30円引き上げるほか、入院基本料も平均2%程度引き上げます。
変わる医療の役割 「治す」から「支える」へ 中日新聞【社説】2月12日
日本は世界一の長寿国になった。高齢化社会では病を「治す」医療だけでは長い人生を支えきれない。医療の役割は大きな転換期にあるようだ。
「食べさせないから死ぬんじゃない。死を迎えるから食べないんです」
あるシンポジウムで、特別養護老人ホームの高齢者を見守るベテラン医師・石飛幸三さんはこう訴えた。医師の思いと患者の実態とのズレを現場で実感したからだ。
現代の医療は病を治し、延命することを使命としている。食事がうまくできないのなら胃ろうで栄養を取り延命を目指す。
◆胃ろう拒否した夫婦
リハビリで回復が見込める場合など胃ろうが必要なケースはあるが、その医療は本当に本人の望むものだろうか。こんな疑問が医療や介護の現場で広がっている。
石飛医師はある夫婦の決断を紹介した。介護施設に入る妻に胃ろうを迫られた夫は拒否した。それが妻のためになると思えなかったのだ。夫は職員と一緒に毎日、食事介助を続け一年半の貴重な時間を共有した。
最期は眠り続け一週間後に息を引き取った。かつて病院で延命治療に取り組んでいた石飛医師が驚いたのは、延命治療を施していないのに最期まで呼吸が苦しくならず尿も出たこと。
「最後の代謝で体中を整理して身を軽くして天に昇っていった」
穏やかな最期だった。
「死なせない」医療は多くの命を救ってきた。それにかかわる人たちの共通の思いだろう。今後はそれに加えて「安らかな最期」を迎えられることも望まれている。それは本人が望むよう生きること自体を支える医療ともなる。
二十世紀の日本の医療は結核などの感染症対策から始まった。全国に保健所が整備され公衆衛生に力点が置かれた。「守る」医療だ。
最初の役割の転換点は二十世紀半ばだ。脳卒中やがん、心臓病などの慢性疾患が死因トップになると医療設備と人材を集約して対応する病院の整備が進んだ。「治す」医療が進歩した。
医療の量が確保され、どこの医療機関にもかかれるようになった。国民皆保険が国民に行き渡りそれを支えている。
◆患者の生活の質重視
高齢化が進む今は次の転換期を迎えているといわれる。病を治す病院の役割は依然重要だが、徐々に体の機能が低下する高齢者には生活の質(QOL)を「支える」ことこそが大切になる。それには在宅医療が不可欠だ。
政府の社会保障制度改革国民会議が昨年まとめた報告書では、今後の医療について二つの構造改革が示されている。
まず、手術などの治療で病やけがを治す急性期の医療や、治療を終え社会復帰へリハビリを担う医療など病院ごとの役割分担を明確にし、同時に在宅医療も充実させていこうとする改革だ。
二つ目はこうした医療機関の再編を都道府県が担うことだ。政府は約九百億円の補助制度を二〇一四年度に新設し、地域のニーズに合った医療体制を整える。
社会保障にも地方分権を進め効率的な医療の提供を図る発想は確かに必要だろう。
政府が二年に一度見直す医療の価格(診療報酬)も在宅医療の充実が図られそうだ。一四年度からの改定内容が十二日に決まる。
医療保険の保険料や税、患者負担から支払われる医療費をどの治療や投薬に配分するかを決める。今改定では在宅医療を担う医療機関や人材を増やす方向である。
二五年に団塊世代が七十五歳を超える。増える高齢者に医療を提供し、充実した老後を過ごしてもらうには今後も在宅医療の充実に努めるべきだろう。
患者を在宅に移せば病院の医療費は減る。その分を在宅医療に回せるよう、自治体は病院再編を確実に進める必要がある。そのために新設される補助金である。医療機関へのバラマキで終わらないよう監視すべきだ。
海外に比べ国民医療費は少ないのに手厚い医療を受けられるのが日本の医療の良さだ。改革はその維持が前提でなければならない。
◆人生そのものを診る
医療が患者の伴走者となるには病だけでなく人生そのものを息長く診る覚悟が要る。処方箋は一つではない。その人に合った多様な医療を提供する技量が要る。介護との連携も不可欠である。医師の再教育など人材育成が課題だ。
患者は軽い症状でも高度医療を行う大病院を受診しがちだ。しかし、不必要な受診を控えるなど患者にも自覚が求められる。医師も患者も互いに顔の見える関係をつくる。どんな人生を送りたいか、それを実現する医療は何か話し合う。人生をともに歩む医療はそこから始まるはずだ。
診療報酬改定―主治医を選ぶためには 朝日新聞社説2月13日(木)
病気の治療だけでなく、予防から介護サービスの使い方まで何でも相談できる。
そうした「かかりつけ医」を誰もが持つ時代に向け、医療界が自己改革し、患者も意識を変える出発点にすべきだ。
医療の公定価格である診療報酬の改定内容が決まった。40兆円近い医療費の配分を見直す2年に一度の改定で、医療の質に大きく影響する。
目玉の一つが、「主治医」の普及を促す新料金だ。診察や検査などの報酬をひとまとめにして、生活習慣病や認知症の患者1人あたり月約1万5千円が医師側に支払われる。患者がかかる他の病院や処方薬をすべて把握するのが条件だ。
今回、消費増税への対応として初診や再診の料金を一律に引き上げたのは疑問だが、患者の生活全体に目配りする主治医に厚く配分する方向性は正しい。
診療所から動こうとせず、患者と目も合わさず、薬を処方するだけ。時間外は一切、対応しない。そんな開業医にまでお金は回せない。
ただ新制度の定着には、個々の医師がバラバラにがんばっても限界がある。地域の医療機関同士で情報を共有する仕組みが必要になろう。
参考になるのが、大阪市浪速区の医師会が4年前から取り組むネットワークづくりだ。
かかりつけ医が、患者の病気や薬、アレルギー歴などを記入した「ブルーカード」と呼ばれる書類を作成し、緊急時に対応を依頼する地域の病院に送るとともに、地区の医師会がデータベース化している。
登録した患者はのべ約700人。病気が悪化して救急車を呼んだ場合、登録先の病院がスムーズに受け入れる。そこでの状況は、医師会とかかりつけ医に報告される。
入院患者が退院する際、医師会がかかりつけ医を紹介する事業も手がける。
集めたデータを病気の予知に役立てることも視野に入れる。医師と患者の一対一の関係を超え、地域全体が有機的につながって安心を生むだろう。
誰を自分の主治医にするか、選ぶのは患者だ。その際、医師の診療科以外でも相談に乗ってくれるか、適切な病院を紹介してくれるか、などが重要な判断基準になる。
最初から大病院に行くのではなく、いざという時に地域の医療と介護のネットワークが頼れるよう、日頃から医師と信頼関係を結んでおく。そんな心構えが求められる。それは結果的に医療費の節約につながる。
診療報酬改定 「病院依存」から転換できるか(2月13日付・読売社説)
病院偏重の医療から、在宅ケア重視に転換する契機となるだろうか。
医療機関の収入となる診療報酬の改定内容が、中央社会保険医療協議会(中医協)で決まった。
重症者を受け入れる急性期病床の要件を厳しくする一方で、早期退院のためにリハビリを重点的に行う病床の報酬を手厚くする。
日本の病院は、患者の平均入院日数が欧米に比べて長い。それが医療費の膨張も招いている。
高齢化はさらに加速する。高齢者の多くが、在宅医療で対応できる慢性病を患っている現状を考えれば、急性期病床を減らし、早期退院を促す狙いは理解できる。
問題は、いかに病床の再編を効率的に進めるかだ。
厚生労働省のこれまでの診療報酬改定は、少なからず医療現場に混乱をもたらしてきた。
急性期病床についても、2006年の診療報酬改定を機に過剰になった。報酬を高く設定したため、多くの病院が必要以上に急性期病床を設けた結果だ。
看護師を多く配置する必要があるため、医療機関の間で奪い合いが生じた。都会に看護師が偏在する傾向も強まった。
急性期病床なのに、入院しているのは病状の落ち着いた高齢者が大半という病院も少なくない。
厚労省は、制度設計が甘かったことを反省すべきである。
今回の改定でも、同様の懸念は拭えない。リハビリ用病床の報酬を高くすれば、これに転換を図る病院が急増するだろう。リハビリ用病床が多過ぎると、本来は在宅ケアで済む患者が、病院にとどまることにつながらないか。
リハビリ用病床が過剰にならないよう、厚労省はしっかりとした対策を講じることが肝要だ。
今回の改定では、在宅ケアの患者の主治医となる開業医への報酬も新設される。在宅療養する高齢者の病状を安定させることが目的だが、大病院志向が強いとされる患者が、開業医をかかりつけ医とするかどうかは不透明だ。
病床再編には、診療報酬改定だけでなく、地域ごとに必要な急性期病床やリハビリ用病床数を正確に算出することが大切である。
政府は、現在の地域医療計画を充実させるために、必要なリハビリ用病床数を盛り込んだ「地域医療ビジョン」を15年度以降、都道府県に策定させる方針だ。関連法案の今国会成立を目指す。
医療機関への指導権限を持つ都道府県が、均衡の取れた病床再編に果たすべき役割は大きい。
中医協 診療報酬改定案を答申 NHK(2月12日)
中医協=中央社会保険医療協議会は、医療機関に支払われる診療報酬について、医療機関の役割分担を進めるため、重症患者に対応する病院が増えすぎていることから、こうした病院への支払い要件を厳しくする一方、在宅医療を担う診療所には加算するなどとした新年度・平成26年度の改定案を厚生労働大臣に答申しました。
医療機関に支払われる診療報酬は、新年度・平成26年度から全体で0.1%引き上げることが決まっており、中医協=中央社会保険医療協議会は、12日の総会で、個別の診療行為ごとの価格を定めた改定案を取りまとめ、田村厚生労働大臣あてに答申しました。
医療機関の役割分担
それによりますと、高齢化を見据えて医療機関の役割分担を進めるため、看護師の態勢を手厚くして重症患者に対応する病院が増えすぎていることから、こうした病院に支払っている高い診療報酬の要件をことし10月から厳しくするとしています。
重症患者に対応して最も高い診療報酬を受け取っている病院のベッド数は現在、全国でおよそ36万床あり、厚生労働省は、新年度からの2年間で9万床減らしたいとしています。
これに対し、重症の状態から回復した患者や比較的症状が軽い救急の患者を受け入れる病院を増やすため、新たな診療報酬を設けるほか、患者の早期退院に向けて、リハビリの知識がある専従の医師などを配置した病院には、1日当たり2000円を新たに加算するとしています。
在宅医療の充実
在宅での医療を充実させるため、1年間で緊急の往診を10件以上、いわゆる看取りを4件以上行っている診療所などに診療報酬を加算するほか、常勤の看護師を7人以上配置するなど充実した態勢や十分な実績がある訪問看護ステーションには、ひと月ごとに最初に訪問した際の診療報酬を最大で5100円引き上げます。
「かかりつけ」の医師
慢性的な病気を抱える高齢者が増えていることから、患者の健康を日常的に把握する「かかりつけ」の医師を増やすため、生活習慣病に加え、認知症のある人などを継続的に診察する医療機関には、ひと月ごとに1人当たり1万5030円の定額の診療報酬を支払うなどとしています。
充実分野
医療の充実が求められる分野では診療報酬を手厚くするとしています。
具体的には、がん患者への精神的なケアとして、医師などが面接を行った場合や投与する抗がん剤を文書で説明した場合に2000円の診療報酬を支払うほか、重い認知症の患者に対し、短期の集中的なリハビリをした場合、1日につき2400円の診療報酬を支払います。
胃に直接穴を開け、チューブで栄養や水分を送る「胃ろう」に関連して、患者が再び口から食べられる状態に高い割合で回復させている医療機関には1850円を加算するほか、胃ろうを取り除いた場合、2万円の診療報酬を支払うとしています。
効率化分野
医療の効率化を図るため、治療以外の目的でうがい薬だけを処方した場合は、全額を患者の自己負担とするほか、薬局についても、同じ医療機関から90%以上、薬の処方せんを受け付けている場合などは、原則として調剤基本料を引き下げるなどとしています。
消費税対応
ことし4月からの消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担を軽減するため、初めて治療を受ける際にかかる初診料と再診料がそれぞれ引き上げられ、自己負担が3割の患者の場合、医療機関の窓口で支払う金額は、初診料が現在より36円増えて846円に、再診料が現在より9円増えて216円になります。
厚生労働省の試算
診療報酬の改定で、患者が医療機関の窓口で支払う金額がどのように変わるのかを厚生労働省の試算を基に見てみます。
<脳梗塞で手術>
脳梗塞で夜間に緊急入院した58歳の男性が手術を受け、翌日からリハビリを行った場合です。手術したあと、ICU=集中治療室に3日間、その後、一般病棟に11日間入院したとします。患者の自己負担は3割です。改定では、集中治療の経験が豊富な医師を配置したICUなどには、高い診療報酬が新たに設けられます。
また、夜間、看護師の補助を行う職員の配置を手厚くした医療機関への加算が設けられます。患者の支払額は、自己負担に上限を設けている「高額療養費」制度が適用されるため、現在より2598円増えて9万1970円となります。
<末期がんの在宅医療>
78歳の男性が末期の肝臓がんのため自宅で療養し、週2回の訪問診療や週4回の訪問看護を受けた場合です。患者の自己負担は1割です。改定では、在宅医療を充実させるため、1年間に緊急の往診を10件以上、いわゆる看取りを4件以上行っている診療所などに診療報酬が加算されます。また、常勤の看護師を7人以上配置するなど、充実した態勢や十分な実績がある訪問看護ステーションには、診療報酬が引き上げられます。患者の1か月当たりの支払額は、現在より870円増えて2万8990円となります。
<複数の生活習慣病で通院>
75歳の男性が、糖尿病と高脂血症で内科の診療所に月2回通い、飲み薬で治療している場合です。患者の自己負担は1割です。改定では、生活習慣病が複数ある患者に継続的な治療を行った診療所には、ひと月ごとに1万5030円の定額の診療報酬が支払われます。また、24時間態勢で調剤を行う薬局への加算も設けられます。患者の1か月当たりの支払額は、現在より590円増えて1870円となります。
高齢者集合住宅で在宅医療
高齢者向けのマンションで暮らす82歳の女性が、高血圧と糖尿病のため24時間態勢で在宅医療を行っている診療所から、入所しているほかの高齢者とともに、月に2回の定期的な訪問診療を受けている場合です。患者の自己負担は1割です。改定では、同じ日に同じ建物で複数の訪問診療を行った場合、診療報酬が引き下げられることから、患者の1か月当たりの支払額は、現在より3990円減って1410円となります。
「医療機関に適正化を迫る内容」
中医協の委員のうち、医療費を支払う側である健康保険組合や連合、経団連などの委員がそろって記者会見しました。
この中で、健康保険組合連合会の白川修二専務理事は「消費税率の引き上げ分を除くと、『マイナス改定』と言え、医療機関に対し適正化を迫る内容だ。重症患者に対応した病院への支払い要件を厳しく見直したことは大変高く評価できる」と述べました。
一方で白川氏は、ことし4月からの消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担軽減に関連して、「初診料や再診料が4%も引き上げられ、消費税率の引き上げ分である3%を超えることは大きな問題だ。消費税の考え方に反する取り決めで、国民の理解は得られない」と述べました。
「メリハリのきいた改定」
日本医師会の横倉義武会長は記者会見で、「主治医機能や在宅医療への手当など、地域に密着した医療への適切な評価が行われ、少ない財源の中で、メリハリのきいた改定になったという印象だ」と述べました。
また横倉氏は、ことし4月からの消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担を軽減するため、初診料と再診料をそれぞれ引き上げることについて、「医療機関に負担が生じないよう補填(ほてん)が行われたことは評価できる。ただ消費税率が10%に引き上げられる場合には、患者の負担を増やすことなく、税制による解決が望ましい」と述べました。