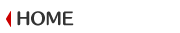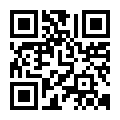活動日誌−活動日誌
【14.01.01】 今日の朝日新聞社説は、「政治と市民―にぎやかな民主主義に」と題して、「来るべき民主主義」の著者國分功一郎さんの考えを展開している。
私が読みかけている本の一つです。
東京・小平市の雑木林に都道を通す計画への異議申し立て運動から、民主主義とは何なのか、政治とは何なのか、哲学の役割を述べています。
ものごとを実質的に決めているのは議会ではなく「行政機関」ではないかという。選挙で議員や首長を選べば民主主義は機能していると思いがちだ。議会は不可欠だが、それに加えて行政を重層的に監視して「それはおかしいと伝える回路が欠かせない」。そのために住民投票や審議会などの諮問機関の改革、パブリックコメントの充実などを提案している。
最後に、「静かな雑木林からの呼びかけに、もっとにぎやかな民主主義で応える新年にしたい。」と締めくくっている。
全文は以下の通りです。
政治と市民―にぎやかな民主主義に 朝日新聞社説2014年1月1日(水)
一面の枯れ葉を踏みながら歩く。その音さえカサカサとあたりに響くようだ。静かな東京・小平市の雑木林。近所の人が散歩などで親しむこの小さな空間が昨年、何度もニュースになった。そこに都道を通す計画への異議申し立て運動が高まりを見せたためだ。
それまで選挙では主要な争点にならず、住民の多くも意識していなかった古い計画だ。その実施が決まったと、あるとき知らされる。計画だけでなく、それを決めて進めるプロセスそのものへも疑問がふくらんだ。住民投票で問うたのも建設の賛否ではなく、決定に住民参加を認めるかどうかだった。だから、地元以外の人々の関心も呼んだのだろう。
運動に参加した哲学者の國分功一郎さんは、ものごとを実質的に決めているのは「行政機関」ではないかという。選挙で議員や首長を選べば民主主義は機能していると思いがちだ。けれど、日々の統治を担う行政府に、市民が異議を申し立てるのが容易ではないとしたら――。
■強い行政、弱い立法
民主主義社会で市民が疑問を感じる政策を政府が進める。昨年暮れ、成立した特定秘密保護法をめぐっても同じような構図があった。しかも、この法律は行政府による情報の独占を可能にする。何が秘密かを決めるのも管理するのも、結局は行政府の人である。肝心の国会は監視できる強い立場を与えられていない。国会で多数派が賛成したから成立したのだが、皮肉なことに、この法律は行政府の権限を強め、立法府を相対的に弱める。行政府が民意の引力圏から一段と抜け出すことになった。行政府が強くなり、立法府が弱くなる。これは必ずしも新しい問題ではない。しかし近年、海外でもあらためて議論されるようになっている。背景の一つはグローバル化だ。カネや情報が急速に大量に国境などお構いなしに行き交う時代、行政府は刻々と変化する市場などがもたらす問題の解決をつねに急がされる。民意はときに足かせと映る。
■「補強パーツ」必要
だからこそ、行政府は膨大な情報を独占し、統治の主導権を握ろうとする。その結果、多くの国民が「選挙でそんなことを頼んだ覚えはない」という政策が進む。消費増税に踏み込んだ民主党政権、脱原発政策に後ろ向きな現政権にそう感じた人もいるだろう。欧州では債務問題に直面した国々の政府が、人々の反発を押し切って、負担増の政策を進めた。だが、議論が割れる政策を採るならなおさら、政治は市民と対話しなければならない。もとより行政府を監視するのは立法府の仕事だが、政治家は閣僚になったり自分の政党が与党となったりすると、行政府の論理に大きく傾く。ミイラ捕りはしばしばミイラになる。
民主主義を「強化するパーツが必要」と國分さんはいう。議会は不可欠だが、それに加えて行政を重層的に監視して「それはおかしいと伝える回路が欠かせない」。そのために住民投票や審議会などの諮問機関の改革、パブリックコメントの充実などを提案する。地味で頼りなさそうな方法に見えるかもしれない。けれども、議会と選挙以外で市民が政治に働きかける手段は海外でも見直されつつあるようだ。
■有権者から主権者に
たとえば、フランスの民主主義研究の大家ピエール・ロザンヴァロン氏は「カウンター・デモクラシー」という言葉で、議会制民主主義のいわば外側にある仕組みへの注目を促す。デモ、新旧のメディア、市民による各種の評議会などを指す。やはり議会は否定しない。それを補完するのだという。豪シドニー大学のジョン・キーン教授も、行政を監視する市民のネットワークや組織を重視する。最近邦訳が出た「デモクラシーの生と死」という著書で、それを「モニタリング民主主義」と呼んでいる。年末の訪日時の講演でも、地球温暖化や少数民族、核軍縮などグローバルな課題で市民レベルの運動が果たした役割を強調した。いずれも投票日だけの「有権者」ではなく、日常的に「主権者」としてふるまうことを再評価する考え方ともいえる。そんな活動はもうあちこちに広がっている。新聞やテレビが十分に伝えていないだけだと批判をいただきそうだ。確かに、メディアの視線は選挙や政党に偏りがちだ。私たち論説委員も視野を広げる必要を痛感する。場合によってはこれから2年半、国政選挙はない。それを「選挙での多数派」に黙ってついていく期間にはできない。異議申し立てを「雑音」扱いさせるわけにもいかない。
静かな雑木林からの呼びかけに、もっとにぎやかな民主主義で応える新年にしたい。