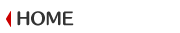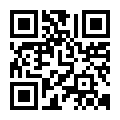活動日誌−活動日誌
【18.01.25】 生活保護費の根拠なき削減 生活保護費削減計画の撤回を
年収階級を10段階に分けた場合の最も低い所得世帯層(年収階級下位10%層)の消費実態と比較・均衡させる手法で引き下げるもの
「子の育成費も確保されない」
10月からの生活保護費削減計画について厚生労働省は、諮問機関である社会保障審議会生活保護基準部会での専門家による検証結果を踏まえたものだと説明しています。しかし、同部会での議論の経過や報告書を見れば、専門家委員の意見にそった削減計画とは到底言えるものではありません。他の研究者からは「今回のように多くの留意点や課題を指摘した報告書はこれまでになく、政府の削減計画には根拠がない」と批判する声があがっています。
厚労省の削減計画は、日常生活費に充てる生活扶助費の基準を、年収階級を10段階に分けた場合の最も低い所得世帯層(年収階級下位10%層)の消費実態と比較・均衡させる手法で引き下げるものです。
この年収階級の下位10%の平均年収は、総世帯では116万円で、2人以上世帯でも193万円とかなり低いものとなっています(2014年全国消費実態調査)。消費支出は、10年間で月額1・3万円減少しています(夫婦子1人世帯)。
生存権守れず
生活保護制度に詳しく、03〜04年には厚労省の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の委員を務めたこともある法政大学の布川日佐史教授(社会保障論)は、この10年間でも年収階級下位10%層の消費支出の低下に合わせて国が生活扶助基準を1・3万円も引き下げてきたことで、生活保護制度が本来の機能を果たさなくなっていると指摘。「いま生活保護は基準の底が抜けてしまっている状況だ」と話します。
今回の社会保障審議会の同部会でも多くの委員から、格差や貧困が広がるなかで低所得世帯と比較する手法では“憲法25条に掲げる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)が守れなくなる”との懸念や異論が噴出しました。
「健康で文化的な生活が保てるかどうかが、今のやり方ではまったく保障できない」(2017年12月8日、首都大学東京・阿部彩教授)
「低所得世帯の消費水準が下がったとしても、これだけは必要であるという額がある。その点からも精査をやっていただきたい」(同日、同大学・岡部卓教授)
日本女子大学の岩田正美名誉教授は、生活保護利用者の実態をしっかり調査することを求め、「そうじゃないと怖い。こんなこと(引き下げ)を決めていいのかと思ってしまう」とまで述べました(同日)。
そして同部会は昨年12月14日にまとめた報告書で、今回の検証方法は「子どもの健全育成のための費用が確保されない恐れがある」ことや、「単に消費水準との均衡を図ることが最低生活保障水準を満たすものと言えるのか、水準均衡方式のあり方が問われる本質的な課題」があることを指摘。具体的に生活扶助基準を見直す時は、検証方法に課題が残っていることに留意し、「検証結果を機械的に当てはめることのないよう、強く求める」と厚労省にくぎを刺しました。
根拠ない計画
それにもかかわらず厚労省は、報告書がまとめられた4日後には、当初案より減額幅を一定抑えただけの削減計画を決めました。
布川教授は「(今回の削減計画は)専門家の意見を聞いたものでもなく、まったく根拠がない。国は、これだけ基準額が下げられてきた中で、まずは生活保護利用者が健康で文化的な生活ができているのかの検証をすべきだ」と語りました。
「低所得との比較でいいのか」
生活保護の生活扶助基準について審議を続けてきた社会保障審議会生活保護基準部会で最終盤に大きな議論となった一つが、生活扶助基準の算定方式として採用している「水準均衡方式」の在り方をめぐる問題でした。具体的には“低所得世帯とのみ比較・均衡させるものでいいのか”という問題です。
昨年12月8日と12日の同部会では、厚労省が示した資料について専門家委員から厳しい意見が相次ぎました。
その資料とは、年収階級を10段階に分けた場合の最も低い所得層(年収階級下位10%層)との比較をもとに算出した高齢世帯の生活扶助基準案で、今回の削減によって、全世帯の平均的な所得層(中間所得層)の消費実態の5割台の水準にとどまることを示すものでした。
平均の5割台
これに対し首都大学東京の岡部卓教授は、「(生活扶助基準は)低所得世帯との均衡をはかる一方で、中位の所得階層の6割をクリアするというのがこれまで合意されてきたことではないか」と発言。他にも「なぜ(中間所得層の)6割(が必要)かというと、先進国の公的扶助の水準がそのぐらいだという考え方。(今回は)かなり下げすぎ」(岩田正美・日本女子大学名誉教授)などの声があがりました。
2003〜04年に厚労省の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の委員を務めた法政大学の布川日佐史教授は、「そもそも水準均衡方式の『均衡』とは、一般全世帯の平均消費支出の6〜7割に、生活保護利用者の消費支出を均衡させることが定説でした」と指摘。厚労省が中間所得層ではなく、年収階級下位10%層との比較を重視することについては、「歴史的経過を一面化した誤った理解だ」と話します。
布川教授の言う「歴史的経過」とは、「水準均衡方式」が導入(1984年)された経過です。「水準均衡方式」以前に採用されていた「格差縮小方式」(65年導入)では、当時一般世帯の消費水準と比べてかなり低かった生活扶助基準の「底上げ」が目的でした。具体的には「一般勤労者世帯の消費水準の少なくとも60%程度を保障する」(70年、厚生省の「厚生行政の長期構想」)ことを目標に掲げていたのです。この目標は達成され、「一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準」と判断されたことから、その後は「妥当な水準」を維持していくとの考え方で「水準均衡方式」に移行しました。
この経過を見れば、生活扶助基準の検証では、一般国民全体の平均(つまり中間所得層)の消費実態との比較・格差が考慮されるべきだというのが、布川教授や専門家委員の主張でした。
社会保障審議会の同部会の報告書には、専門家委員の要求で新たな生活扶助基準案と中間所得層の消費実態の比較表が盛りこまれ、高齢世帯の基準額が中間所得層の「5割台になってしまうことが見込まれることに留意が必要」と注文をつけました。
計画の撤回を
しかし厚労省が昨年12月22日に示した削減計画では、生活扶助基準額と中間所得層との比較については一言も触れられておらず、審議会の注文に応える姿勢は見られません。
布川教授は「これは水準均衡方式の本質に関わる問題です」と批判し、こう訴えました。「5割台になる世帯が健康で文化的な生活を営めるとはいえません。中間所得層との格差を拡大し、固定化する今回の引き下げは認めることはできない」
(この連載はしんぶん赤旗1月24日・25日、前野哲朗氏が担当)